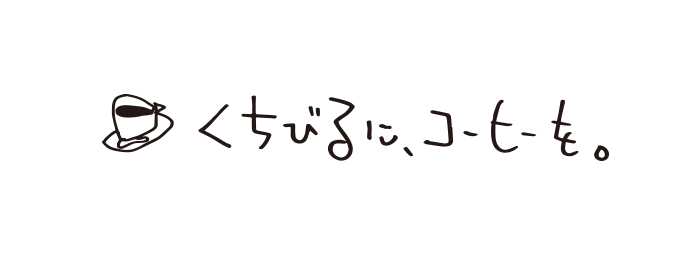今日は会社の創設記念日だそうで、ポンと不意に休みができてしまった。
普段カレンダー通りに働く僕にとって平日の休みは初めてのことで、どうして良いかわからず、”暇をもて余す”を絵に描いたような状況だ。
地元とは決して呼べない、寝に帰るだけの町の平日昼間、夕方の情報番組で芸人が食べ歩きをしていそうな商店街を徘徊している。
この通りは昔からの店が多く、僕が帰る頃にはほとんどの店が閉まっている。踏み切りの反対側(つまり西側)は逆に新しい飲み屋が多く、週末は地元民らしき人たちで賑わっているようだ。
昼間の商店街は僕にとって物珍しく、カメラは回ってないけどロケのような気分で地元を歩いていた。まだまだ地元と呼べるような間柄ではない町が、歩くたびに体に入ってくるような気がした。
・・
肉屋の店頭でコロッケが揚げられていて、それを横目に自転車を避けた時、前から歩いてきた男が低い声で僕に言った。
「ごめんなさいよっ」
実は少し前から視界に入っていた。
ヨレヨレのTシャツにボロボロのジーンズ、腰から巾着がぶら下がり、雪駄を擦りながら歩いてきた。いや、歩くと言うよりも踊っていた。まさか話しかけられるとは思っていなかった僕はとっさに「あ」とだけ返した。
すれ違い際にほんの少し白檀の香りがした。
通り沿いの100均で洗濯バサミを買い、隣の本屋で雑誌を手に取り、向かいの喫茶店で休憩することにした。晩は王将にでも行こうかと考えていたのでその時間までの休憩だ。
この喫茶店も会社帰りに前を通ることはあったけどその時間には閉まっているし、いつもカーテンが掛かっていて中が見えない。今日も中が見えないけど、こういう昭和の喫茶店に出入りすることが地元民への第1歩のように思えた。
・・
「いらっしゃい」
意を決してドアを開けると女性の声が静かに出迎えてくれた。店内の暗さに目が慣れるまで時間がかかったけど、木調の落ち着いた店内は奥に長くカウンター10席ほどの広さだった。
僕はカウンターの中ほどに座った。一番奥では初老の男性が文庫本を読んでいる。
「何しましょ?」
70代くらいのママさんがにっこりと微笑み、お冷やと布おしぼりを出してくれた。
「アイスコーヒー、ブラックでお願いします。」
僕はメニューも見ずに注文した。特にアイスコーヒーが飲みたかったわけではないけど、せっかくの平日昼間の商店街、地元民への憧れを存分に楽しんでいた。
流行りのコーヒーとは真逆の、濃くて苦いコーヒーを飲みながら店内を見渡たす。古びたスピーカーからはピアノジャズが流れ、メルヘンな置物や地方のお土産らしきもの、棚の隅には文庫本が並び、壁には町の祭りのチラシが貼ってある。
「おう、冷コおくれ!」
突然ドアが開いたかと思うと、さっきの男が駆け込んできた。全く立ち止まりもせず流れるようなステップで椅子に腰をかける。おそらくいつもの席なのだろう。
よりによってそれが僕の左隣だった。
・・
踊るような動き、初夏の日差し、ラフな服装があいまって男の白檀臭は最高の状態で醸し出されていた。椅子に座ってからもほんの少しだけ揺れている
「今日もやってるの?」とママさんはいつもの調子で男に聞く。
「おう、こういうのは天気も曜日も関係ないからな」ストローも使わずに男はアイスコーヒーに口をつける。涼しげに氷の音がカランと鳴り響く。
「今度、祭りがあるじゃない。盆踊りもあるみたいだけど、りとるは踊らないの?」ポットにお湯を継ぎ足しながらママさんは男に言った。
「いや、あれは全然違う。俺は踊りをやってるんだぜ」
「だから言ってるのよ、盆”踊り”だって」
「ママ、区切るところが違う。あいつらは“盆踊り”を踊るんだ」
「あ、そっか、そうね」と言ってママさんは笑った。
空中ではピアノに合わせてサックスがソロで唸っていた。
・・
二人の会話は「前回の続き」から始まっていた。
文脈というか関係性というか、その町で暮らす日常の中のひとコマが目の前で切り取られ、僕は物語のワンシーンにだけ登場するエキストラのようだった。
降って湧いたような平日の昼間、縁あって移り住んだ町の片隅で繰り広げられる物語に僕も参加したかった。憧れが現実になる境目に自分が今いることはわかっていたし、あとはもうタイミングだけだった。
薄暗い店内と盛り上がるジャズ、白檀の香りと苦いコーヒーが重なった時、僕は勇気を出して男に話しかけた。
「あの、、すみません。踊りと踊るって違うんですか?」
男はグラスを置いて首を捻り肩越しに僕を確認すると、椅子をぐるっと回転させて体を少し僕に寄せた。豪快に見えた彼が初対面である僕にはやや気を遣い、少し間を持ってゆっくりと口を開く。
「俺はね、踊りをやってるの。毎日、朝から晩まで。平日も休みの日も。」
おそらく自分の言っていることが周囲に伝わりづらいことをわかっているのだろう。ゆっくり、区切って話してくれた。
僕が頷き、言葉を飲み込んだのを確認してから男は続けた。
「だからな、りと、る、はな、全然違うんだ。」男は僕の目を見ながらゆっくり、丁寧に区切って言った。
「ありがとうございました〜」
ママさんの明るい声が店内に響き、奥にいた初老の男性が僕らの後ろを抜けて外へ出ていく。
開いたドアからは少しむんとした町の空気と一緒に夕暮れの西日が差し込み、グラスの水滴が孔雀のコースターに輪っかを作っていた。
(つづく)